「癇癪持ち」の意味とは?

怒りがすぐ爆発してしまう人
「癇癪」とは、怒りの感情をコントロールすることができずに、激しく声を荒げたり、泣きわめいたりするほど取り乱すことを意味しており、「癇癪持ち」とは、このような性質を持つ人のことを指します。怒り方が尋常ではなく、些細なことでも激怒するという特徴があり、周囲からすると対応しづらい相手であることには違いありません。
とんでもない裏切りや仕打ちを受けて取り乱すのは癇癪とは言いませんが、些細なことでもすぐ取り乱して騒ぐタイプは癇癪持ちだと言えるでしょう。
癇癪持ちは子どもだけではない
癇癪持ちは子供に多いというわけではありません。大人の癇癪持ちも多く、子供よりも大人の方が厄介です。子供の体は小さく力も弱いため、癇癪を起されても周囲の大人だけで対応することができ、大きな問題にはなりにくいものです。しかし、大人の癇癪持ちが周囲の人や物に当たり散らすのを制止するのは困難です。
自分の思い通りにいかずに癇癪を起こしてしまうのは、まだ上手く気持ちを伝えることができない子供だけではないことを理解しておきましょう。
大人の場合、人間関係に問題が生じる場合も
大人の癇癪持ちだと、怒りがおさまらずにいろいろな場面で失敗することもあり得ます。仕事や人間関係に支障をきたすようになり、うつや体調不良などの二次症状が出てくる可能性があるので要注意です。子供の場合は親や教師、支援センターなどの助けを求めることができますが、大人は自分で解決していかなければなりません。
子供よりも、大人の癇癪持ちの方が深刻であり、早急に何らかの対応を求められるのですね。
癇癪持ちは遺伝とは無関係
癇癪持ちの子供がいる親は「遺伝なのでは?」と気にすることが多々あります。しかし、癇癪持ちと遺伝の関係性は医学的に立証されていません。また、発達障害のような症状を持っている子供は、感情のコントロールが難しいため癇癪を起こすことがあると言われていますが、「発達障害=癇癪持ち」ということでは決してありません。
癇癪持ちも発達障害も遺伝ではないのです。子供が癇癪持ちだからといって、自分を責めるのはやめておきましょう。
子どもが癇癪を起してしまう原因とは?

自分の感情を整理できない
大人は嫌なことに対する対処方法を身につけていることが多く、さらに自分自身はどういう人間かということもある程度は理解しているでしょう。しかし、子供は自分がどのような人間なのかが分からない上、嫌なことがあった場合の最良の方法を確立していません。嫌なことに対して自分の感情をどのように整理して良いのかが分からないのです。
言いたいことをどのように表現すれば理解してもらえるのか、したいことをどのようにすればスムーズにできるのかが分からない上、上手くいかない場合の感情をコントロールできないのですから、癇癪を起こしてしまうのは仕方のないことなのかもしれませんね。
疲れや空腹が原因であることも
大人は疲れていると「今日は早く帰って早く寝よう」などと調整したり、空腹であると「コンビニに買いに行こうかな」「家にあるものでサッと作ろうかな」と簡単に問題を解決することができます。子供はまだ自分がどのくらい疲れているのか、どのように疲れをとれば良いのかが分かりません。
さらに空腹だからと言っても、周囲の大人に何とかしてもらわなければ、食べ物を買うことも作ることもできないのです。自分だけで解決できない場合、子供は癇癪を起こして自分の不快さを訴えるようになるのでしょう。この場合、癇癪の解消のために周囲の大人のフォローが必要です。
環境の変化についていけない
「ストレス」と聞くと「嫌な思いをする」というイメージが先行しがちですが、ストレスは環境が変化するだけでも溜まっていきます。人生経験の少ない子供なら、なおさら環境の変化についていけずにストレスを溜めてしまうのですね。
「幼稚園に入園した」「小学校を転校した」「引っ越しをした」などもそうですが、下に兄弟が生まれて急に「お兄ちゃん」「お姉ちゃん」であることを求められる時もストレスを感じているはずです。自分で上手くストレスを処理できないため、癇癪を起こしてしまいやすくなるのでしょう。
必要な栄養素が足りていない
成長が落ち着いて体ができあがった状態の大人とは違い、子供は急激に成長しています。この時期の食生活は非常に重要であり、必要な栄養素が足りていない場合、癇癪をおこしやすくなると考えられます。大人でも体調が悪い時はイライラしやすいものですので、感情のコントロールが上手くできない子供なら、なおさらだと言えるでしょう。
子供は糖分が好きですが、摂りすぎると体が血糖値を下げようとして結果的に低血糖になり、イライラしやすくなってしまいます。また野菜や乳製品を嫌う子供も増えましたが、カルシウム不足でやはり癇癪を起こしやすくなります。お菓子を食べすぎていないかなど、食生活を振り返り、バランスの取れたメニューを考えてみましょう。
癇癪持ちになりやすい大人の特徴とは?

真面目な性格
何事にも真摯に向き合う真面目な性格の人は、それ自体はとても素晴らしい特徴だと言えるでしょう。しかし、真面目であるがゆえ、いわゆる「手抜き」「諦め」が一切できないという一面もあります。仕事でもなんでも手を抜きませんし、簡単に諦めることは望ましくないと考える傾向があります。
しかし、人生には失敗はつきものであり、予定通りにいかずにむずがゆい思いをする場合もたくさんあります。そんな時も「絶対に予定通りにしないと」と思い込んで自分を追い詰めてしまい、どうにもならなくなった時に癇癪を起こしてしまう可能性があるのですね。良い意味での手抜き、諦めは人生に必要だと言えるでしょう。
自己表現が苦手
癇癪を起こしやすい子供は、基本的に自分の思っていることを上手く表現できないもどかしさから癇癪を起こすことが多いです。子供に限らず、大人でも自分の思っていることを表現するのが苦手な人は少なくありません。
自己表現が苦手な人も、上手く伝えられない苛立ちで癇癪を起こしてしまう可能性があると言えるでしょう。紙に書いて気持ちを整理する、周囲に相談してみるなど、対処方法を確立させていきましょう。
何でも我慢してしまう
大人は子供とは違い、理不尽な状況でも時に我慢しなくてはならない場合が出てきます。しかし何でも我慢してしまう性格だと、ストレスをどんどん溜め込んでしまうため、限界を超えると癇癪を起こし出す危険があると言えます。
相手の言うことを何でも聞けば「良い人」と思われる、というわけではありません。間違った認識の「良い人」になろうと努力することは止めて、自分の意思をしっかりと表現するようにしてください。
完璧主義である
すべてを完璧にこなしたいという特徴がある人も、癇癪を起こしやすいでしょう。どんなに優れた大人でも、人生において完璧はありません。失敗もし、挫折も味わい、目標を達成できないことも多々あるのです。「完璧にしたい」はあくまで理想であり、そうなるとは限らないということを理解しておかなければなりません。
劣等感やコンプレックスがある
劣等感やコンプレックスがある大人は、常に「人からバカにされているのでは」「攻撃されたら仕返ししないと」と身構えています。少し指摘されただけでも「攻撃された」と思い込み、癇癪を起こして抵抗するため、周囲は対応に困ることも多いでしょう。
このような特徴のある大人は、まず劣等感やコンプレックスを克服するところから始めないといけません。
「癇癪持ち」な人に対する周りの印象

癇癪持ちの人には耳の痛い話だと思いますが、癇癪持ちを改善するいいきっかけになるかもしれません。ぜひ目を通してみてください。
付き合いづらい
「みんなと和気あいあいと話していたのに、いきなりキレだして周囲が凍り付いた」(23歳/男性/営業職)
「少しでも意見を言うと怒りだすため、もうどう付き合っていいのか分からない」(27歳/男性/自営業)
平和な雰囲気の中、突然怒りだされると雰囲気が丸つぶれです。怒るポイントがよく分からないことも珍しくありません。少しでも自分の意見を否定されると相手を怒り散らすわけですから、周囲はどう付き合っていいのか分からなくなってしまうのですね。これでは対人関係で苦労してしまうでしょう。
大人なのだから冷静に対応してほしい
「くじ引きで癇癪持ちの同僚に幹事が当たってしまい、終始不機嫌に。何を話しかけても怒り口調で、腹が立つというより呆れた」(36歳/男性/公務員)
「先輩が上司とケンカして、仕事中なのに帰ってしまった」(26歳/男性/設計士)
大人になると、嫌な役割でも引き受けたり、機嫌が悪くても周囲には当たらないようにしたりするものです。どうしても嫌だというのなら、周囲が納得のいく理由を説明するべきであり、癇癪を起こして当たり散らすことはしてはいけません。大人なのですから、ここは冷静に対応し、関係のない周囲に迷惑をかけることは止めるようにしましょう。
一緒にいて恥ずかしい
「取引先の人の前で同僚が癇癪を起こし、自分たちがひたすら謝る羽目になってしまった」(34歳/男性/営業職)
「合コンで店員に文句をつけ、最終的に癇癪を起こし、雰囲気が最悪に」(27歳/女性/事務員)
自分の思い通りにならないからといって大人げなく当たり散らしたり癇癪を起こしたりする人と一緒にいても、周りは恥ずかしいだけです。周囲の人は、とばっちりを受けてしまわないよう、癇癪持ちの人と距離を取って深入りしないようになるでしょう。
面倒くさい
「嫌な仕事が自分にまわってきたら、机や椅子を叩いたりして不機嫌をアピール。見かねた周囲が交代した途端に上機嫌になった」(29歳/女性/コールセンター)
「常にご機嫌取りをしないと意地悪をしてくる先輩がいる。気にいらない後輩にはすぐ癇癪を起こして怒鳴っている」(25歳/女性/経理)
癇癪を起こしてしまう特徴のある人は、自分の思い通りに事が運ばないと気が済まいない場合が多いものです。周囲は顔色をうかがいながら対応しないといけないため、とても面倒くさい相手だと思っているでしょう。癇癪持ちの人の気分に振りまわされる周囲にとっては迷惑な話でもあります。
癇癪持ちを改善する方法

そんな方のために、こちらでは癇癪を改善する方法をご紹介します。癇癪で悩まされている人は、ぜひ参考にして実践してみてください。
バランスの良い食事をとる
毎日の食生活が今日の体を作っているので、バランスの取れた食生活が大事なのは大人も子どもも同じだと言えるでしょう。栄養バランスが悪いと、必要な栄養素が足りずにイライラしやすくなってしまいます。魚や野菜、果物などを食事メニューに取り入れ、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンなどの物質が分泌されやすいようにすることもおすすめです。
お菓子やカップラーメンは控え、暴飲暴食を避けることも必要です。まずは日頃の食事内容について見直してみましょう。
適度に運動する
癇癪持ちと運動に何の関係があるの?と疑問に思う人もいるでしょう。適度に運動すると脳の血流が良くなり、脳が活性化されます。また、脳が活性化されると幸せホルモンであるセロトニンの分泌も正常に行われ、思考力ややる気が継続する上に、運動による達成感や気分転換が心に良い影響をもたらすことが分かっています。
運動不足は血流が悪くなるため、疲れがなかなか取れません。疲れやすく、疲れが取れにくいため、ストレスが溜まりやすいのです。また、体が疲れていないのに脳は疲れるという現象も起こりやすく、体と脳の疲れがアンバランスになり、不眠を引き起こす恐れがあるので注意しておいてください。
ストレス解消法を身につける
性格は千差万別ですから、ストレス解消法は人それぞれだと言えます。音楽が好きな人、旅行が好きな人、スポーツをすることが好きな人、マッサージが好きな人、それぞれ自分がリラックスできる、リフレッシュできるストレス解消法を身につけておきましょう。
ストレスは、生きている限り多かれ少なかれあるものですよね。そのため、ストレスのない人生を目指すよりも、ストレスをこまめに解消する技を身につけることが重要です。
自分が癇癪持ちであることを理解する
癇癪持ちの人すべてが「自分は癇癪持ちだ」と自覚しているわけではありません。自分が癇癪持ちだと思っていなければ、癇癪持ちを改善することはできないのです。周囲の意見や癇癪持ちの特徴を改めて振り返ってみて、まず「自分は癇癪持ちの特徴をいくつか持っている」「人に迷惑をかけているかもしれない」ということに気づかなければならないのです。
何だか周囲と上手くいかないな、自分の気持ちを上手く伝えることができないなと感じているのなら、癇癪持ちの特徴がないか自己分析してみましょう。
なぜ自分は癇癪を起こしたか考える
癇癪を起こす時、どんなことに対して癇癪を起こしていますか。癇癪持ちの人は、すべての出来事に癇癪を起こすわけではありません。自分は何が原因で癇癪を起こしてしまったのかを、まず考えてみましょう。
プライベートでは我慢できるが、仕事にはこだわりがあって職場で癇癪を起こしやすい、あるいは外では我慢できるが、家では癇癪を起こしやすいなど、自分のパターンを分析するのです。さらに、癇癪の原因が相手にあるのか自分にあるのかを見極めるようにしましょう。相手に落ち度はないのに、単に当たり散らしてしまっているだけなのかもしれません。
自分に問題はなかったか、周囲に相談できそうな相手はいるのかを考えてみましょう。
専門機関に相談する
癇癪持ちの人は、単なる性格ではなくメンタルに問題がある場合も考えられます。養育環境も大きく影響する要因であり、愛着障害や境界性パーソナリティー障害などを発症しているケースも否定できません。まずは、自己診断してしまわず、心療内科などの専門機関に相談し、専門医師の指示を仰ぐようにしましょう。
「こんな自分が嫌だ」「でも直せない」という葛藤で苦しみ続けるよりも、まず治療が必要なのかどうかを確認しておくと、今後の方針を立てやすいのではないでしょうか。
癇癪持ちな人への対応方法《子ども編》

ここでは、癇癪持ちの子どもへの対処法をご紹介します。頭の隅に入れておいて、いざというときにうまく対応できるようにしておきましょう。
癇癪を起している原因を考える
子供はまだ自分の気持ちを上手く表現することができません。そのため、自分の思いが伝わらず癇癪を起こしてしまうのですね。子どもが癇癪を起こした場合は、周囲の大人ができるだけ気持ちを汲み取るようにしてあげましょう。
「まだ遊びたかったのではないか」「親が子どもの話を聞かずに忙しそうにしているからではないか」「おもちゃを他の子にとられたからではないか」など、考えられる原因を探してあげましょう。最初は理解することが難しくても、ある程度癇癪を起こすパターンが分かってくるはずです。根気よく続けてくださいね。
抱っこして背中を撫でる
子供は、一度癇癪を起こしてしまうとなかなか止まりません。癇癪を起こした原因に苛立っているというよりも、周囲が自分の気持ちを理解してくれないことが辛いのです。何を言っても、何をやっても子どもの癇癪がおさまらない場合は、一旦抱っこして背中を撫でてあげましょう。子供は自分を抱きしめてくれる存在に安心し、落ち着きを取り戻してくれます。ぜひ試してみてください。
望み通りにするのはNG
その場をおさめたい一心で、お菓子をあげる、ゲームをさせる、おもちゃを買うということをすると、癇癪が直らないどころかエスカレートしてしまいかねません。癇癪に負けて本人の思い通りにしてしまうと「癇癪を起こせば思い通りになる」という間違った学習をしてしまい、癇癪が直らなくなってしまうのです。
子どもの望み通りにすることは、その場限りの解決法でしかありません。なぜ今は望み通りにしてはいけないのかを根気よく説明し、落ち着かせるようにしましょう。
気持ちを推測し代弁してみる
子供はまだ自分の気持ちを上手く表現できません。癇癪持ちの子供になぜ癇癪を起こしているのか説明しろと言っても無理なのです。「こうしたかったの?」「これが嫌だった?」などと、子供の気持ちを推測しながら代弁してみてください。子供は癇癪を起こした原因をなくしてもらうことよりも、周囲に自分の気持ちを理解してもらうことを求めています。
「自分の気持ちを理解しようとしてくれている」と実感することで安心し、落ち着いていくでしょう。
子育て支援施設に相談する
子供の性格や特徴は様々であり、子育てに正解はありません。自分ひとりで解決法を探っていても途方に暮れてしまうこともあるのです。周囲の友人に相談することも大事ですが、まずは子育て支援施設に相談してみましょう。保育士や助産師、あるいは小児科の医師やカウンセラーなどからアドバイスを受けることができ、一緒に問題を解決してもらえるかもしれません。
1人で子育てしようと無理すると、行き詰ってしまいます。無理しないで頼れることは頼っていくようにしましょう。
癇癪持ちな人への対応方法《大人編》

落ち着いて話を聞く
癇癪持ちの人は、大人でも子供でも「自分の思い通りにいかない歯がゆさ」から癇癪を起こしてしまいます。ですから、意見や批判ばかりぶつけるのは逆効果です。とりあえず落ち着いて話を聞くようにしましょう。癇癪持ちの大人が癇癪を起こし出したら、まず落ち着かせることが大事なのです。
落ち着いた状態で、相手の言い分をすべて聞きましょう。そして、こちらも落ち着いた口調で意見を伝えます。一方的に癇癪を受けるのではなく、冷静に話し合える状態に持っていくようにしてください。
相手が冷静になるまで待つ
癇癪持ちの大人が癇癪を起こし出したら、なかなか収まりません。その状態のときは何を言っても無駄です。とりあえず怒りが収まるまで、そのまま待ちましょう。癇癪持ちの人に怒り返すことは、くれぐれもしないようにしてください。癇癪持ちの人に怒っても、火に油をそそぐ結果になる可能性も否定できません。
とにかく相手が冷静になるまで待ちましょう。一旦その場を離れるなど、急がず時間をかけます。その間に周囲に相談しておき、本人とは対峙しないようにして心がけてください。
アンガーマネジメントを教える
癇癪持ちの大人は、自分が癇癪持ちで良いと思っているわけではないのです。本人も癇癪持ちの性格を直したいと思っている場合が多く、直したいのに直せない状態に陥っているということも考えられます。その場合、アンガーマネジメントを教えてあげましょう。
アンガーマネジメントとは、怒りをコントロールする心理療法の1つです。怒りのアドレナリンが出ているとされる最初の6秒間をどうにかやり過ごし、怒りを抑えます。その場を一旦離れたり、深呼吸をしたりすることで、冷静さを保つことができる方法があることを教えてあげてください。
相手にせず距離を置く
相手が癇癪持ちだからと言って、周囲は何が何でも我慢しなければならないわけではありません。距離を保てる相手であれば、極力関わらないようにしましょう。人間には相性があり、適度に距離を置いて付き合うことは悪いことではありません。人間関係を上手く保つためにも、苦手だと感じる人とは距離を置いて、あまり深入りしないようにしてください。
癇癪持ちと上手く付き合うポイントとは?

こちらまで感情的にならないよう注意する
相手が癇癪持ちだからと言って、同じ土俵に立ってはいけません。癇癪持ちに怒りを倍返しにしても解決はしませんし、それどころか周囲から同等に見られてしまうリスクもあります。一方的に癇癪を起こされると悔しくなる気持ちは分かりますが、せめて自分だけは感情的にならないようにしましょう。
相手は興奮しているので、興奮が収まるまでひたすら待っていましょう。こちらが落ち着いた対応をしていれば、周囲はどちらが真っ当なのか、きちんと判断してくれるはずです。
子供の癇癪はよくあることと理解する
癇癪持ちが子供である場合は、ある程度は仕方のないことだと思うようにしましょう。大人だって上手く伝えることができずに分かってもらえない場合、とても悔しい気持ちになりますね。感情のコントロール方法が身についていない子供ならなおさらなのです。癇癪を止めてほしい一心で子どもを怒るのはやめましょう。
ダメなことはダメと毅然とした態度で教えることは必要ですが、まずは子供の気持ちを汲み取るように努力したいところです。
適切な距離を保つ
距離を置くことができる相手と、できない相手がいます。たとえば、職場の同じプロジェクトの上司であれば、距離を置くことはできません。しかし、癇癪持ちの特徴がある人と親密に付き合うと、辛いことも多いですよね。癇癪持ちの人と距離を置くことができない場合は、たとえば仕事ではしっかり相談しながら進めるが、プライベートでは一切関わらないなど、適切な距離を保つようにしてください。
もしその癇癪持ちの人が仲良しグループの一人ならば、グループでは会うけど2人だけでは会わないなど、「仲は良いけど、深い付き合いはしない」という関わり方をおすすめします。
とりあえず同調しておく
癇癪持ちの人が何か言い出した時は、自分に悪影響が及ぶ話でない限り、とりあえず同調しておくのも手です。癇癪持ちの人が同僚の悪口を言い始めたら、決して話には乗らずに「へえ、そうなんですねー」と同調だけするのです。「そうそう!」などと話に乗ると「あの人も悪口を言っていた」と言われかねません。波風を立てない程度に同調し、話を受け流すようにしましょう。
ポイントを押さえれば癇癪持ちの人とも付き合える
周囲に癇癪持ちの人がいると困ることも多いですが、相手が癇癪持ちだからと言って、付き合いを避けることはできない場合も多々あります。癇癪持ちの人の特徴を理解し、上手く付き合うポイントを押さえる必要があるのですね。
癇癪持ちの人に振りまわされることなく、上手く付き合うようにしていきましょう。



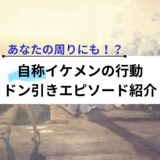




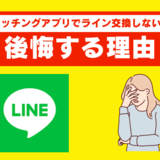
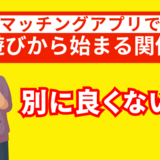
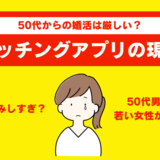






スゴレンは、「男女の恋愛の本音」を集めた恋愛アンケートに基づいて作成した女性向け恋愛コラムを提供しております。さまざまな恋愛シーンで活用できるコンテンツを配信中!