\スゴレン厳選◎人気ランキングはこちら/

笑い上戸な人の特徴&心理とモテる理由|好き?嫌い?周囲の印象とは
よく笑う人を指して「笑い上戸だね」なんて言いますよね。明るい人という印象があり、モテるとも言われます。今回は、そんな笑い上戸な人の特徴と心理、さらにモテる理由を徹底分析。また、笑い上戸な人が周囲に与える印象についてもご紹介します。
目次
そもそも「笑い上戸」ってどういう意味?

「笑い上戸」には二つの意味がある
実は「笑い上戸」には二つの意味があり、一つ目は、お酒に酔うとやたらに笑う癖がある人のこと。もう一つは、何かにつけてよく笑うの人のことを言います。
一般的には、よく笑う人を笑い上戸だと考えている人が多いでしょう。けれど、普段は寡黙なのに、お酒が入ると人が変わったように笑う癖を持っている人も、実は笑い上戸。
笑い上戸に、2つのタイプがあることを初めて知ったという人は、意外と多いかもしれませんね。
そもそも何から生まれた?笑い上戸の語源とは?
お酒が飲めない人を「下戸(げこ)」と言うことを、ご存知でしょうか。笑い上戸の意味にお酒がかかわっていましたが、語源にもお酒が関係しています。
平安時代には家族構成や資産によって家を分類し、納税額が多い家を上戸、その下に中戸、最も納税額が少ない家を下戸に分けました。
この階級によって祝いの席で出せるお酒の量も定められ、上戸の家は8かめ、下戸の家は2かめ。つまり、上戸ほどたくさんお酒を飲めたわけです。
階級によって飲めるお酒の量が違ったことが、だんだんとお酒を飲めるか飲めないかという意味へと変化。さらにお酒を飲むと笑う癖から、よく笑う人のことも「笑い上戸」と呼ぶようになっていったとされています。
笑い上戸な人の特徴&心理《パート1》

明るい性格のポジティブ思考
笑い上戸な人の最大の特徴が、明るい性格だということ。さらに、その心理も全体的にポジティブです。そもそも、ポジティブな心理と明るい性格の持ち主だからこそ、ちょっとしたことにも笑えるのでしょう。何かにつけて後ろ向きにとらえ、ネガティブなことばかり考えていては、笑えるはずもありませんよね。
ただし、笑い上戸な人の場合は、ポジティブでいようと意識しているわけではないため、深く考えずにとっている言動が多いのも特徴です。その結果、いい加減な印象を与えることがあります。
笑いのツボが人より浅い
同じ出来事を見て、笑う人もいれば笑わない人もいます。その違いは、おもしろいと感じる基準の違い。よく言われるのが、笑いのツボですね。
笑い上戸な人は、この笑いのツボが浅いのが特徴。そのため、ちょっとしたことでもすぐに笑います。一方、おもしろいと感じる基準値が高い人、つまり笑いのツボが深い人は、そう簡単には笑いません。
笑いのツボは、足ツボ刺激をする場合のツボとは違って、実際にあるわけではありません。そのため、「笑いのツボが浅い」というのは、「笑い上戸な人がおもしろいと感じるストライクゾーンが広い」と考えると、納得できます。
素直な性格だからつい笑ってしまう
笑い話を聞かされたとき、素直におもしろいと感じる性格なら、率直に笑えるでしょう。笑い上戸な人は、素直な性格の持ち主が多いのも特徴です。人の話を素直に受け止めるからこそ、笑えると言えます。
一方、「その話、本当なのかな?」と何でも疑ってかかる性格だと、なかなか笑えません。あれこれ疑ってかかっていたら、どんな笑い話を聞かされても笑えないのは無理もないでしょう。
笑い上戸な人は、何か裏があるのではないかという心理を持つことなく、物事を素直に受けとめるのが特徴。そのため、おもしろければ疑うことなく素直に笑います。
顔つきがやわらかい
女性の中には、「いつも笑っていると目元に笑いじわができるのではないか」と心配する人もいるのではないでしょうか。
笑うときは顔の筋肉、いわゆる表情筋を動かします。そのため、笑い上戸な人の顔は柔らかいのが特徴。その理由は、たくさん笑ってよく筋肉を動かしているからですね。しわを作りたくなくて無表情でいるほど、表情筋が硬くなり、かえってしわが目立つと言われています。
よく笑う人に見られる目じりのしわは、他人の目には好ましく映るもの。そんな柔らかそうな顔つきには親近感がわきやすく、モテる要素の一つとなっているのでしょう。
笑い上戸な人の特徴&心理《パート2》

いつもニコニコしている
笑い上戸な人は声をあげて笑っている時だけでなく、いつもニコニコしている印象を与えるのが特徴です。顔そのものの柔らかさもあって、ちょっと微笑んだだけでニコニコした顔つきに見えます。
また、笑い上戸な人であることを知っている周囲の人たちからすると、いつ笑い出すかわからないという印象もあるでしょう。そんないつも笑いだしてもおかしくない人というイメージが、常にニコニコしているという印象を与えている可能性もあります。
無意識に笑顔になっている
笑い上戸な人にとって、あらゆることが笑いのタネになるのですから、仏頂面でいる方が難しいのではないでしょうか。そのため、自分でも意識しないまま、笑顔になっていることがよくあります。
本人は自分が笑顔を浮かべていることに気づいていないので、「何か楽しいことあった?」などと聞かれやすいのも笑い上戸な人の特徴。特に何もないのにそんな風に聞かれたのがおかしくて、「え、なんで?何もないけど」と答えてはまた笑う、といった具合です。
笑い上戸な人が無意識のうちに笑顔になっているのは、まさにポジティブな心理の表れと言えるでしょう。
面白いことや楽しいことを探している
笑い上戸な人は明るい性格の持ち主で、思考もポジティブです。この性格の特徴が、常に何か面白いことはないかと探す心理につながっていると考えられます。
常にアンテナを張り巡らせている状態だと、いち早く面白いことを察知できますよね。見つけたが最後、笑いのツボのスイッチが入り、笑いが止まらなくなるかも。
いつも楽しいことを探すという心理は、前向きな思考でないと持てないでしょう。まさに、笑い上戸な人ならではの特徴です。
楽観的に考えている
よく笑う人は、楽観的な性格の持ち主でもあります。特に笑い上戸な人は、物事を楽観的に考え、「なるようになるさ」ととらえるのが特徴です。
この楽観的な心理が、よく笑うという行動につながっているのは間違いないでしょう。人は不安や心配事があると、どうしても笑えなくなるもの。あれこれ考えすぎる性分の人は、笑顔が少なくなりがちです。
ちょっとしたことでも笑えるというのは、それだけ心配や不安を溜めこまない性格だから。笑い上戸な人は楽観的なものの考え方で、ネガティブな感情よりもポジティブな気持ちを優先させられるのが特徴です。
笑い上戸な人をどう思う?【好き派の意見】

笑い上戸な人をどう思うかと尋ねたら、おそらく好き派と嫌い派に分かれるでしょう。そこで、まずは「笑い上戸な人は好き」と答えた人の意見からご紹介します。
一緒にいるとこっちまで笑えてきて楽しい!
「笑い上戸な人と一緒にいると、こっちまで笑えてきますよね。特別おもしろいことがあるわけでもないんだけど、笑われるとつられて笑っちゃう。楽しい気分になれるから好きです」(24歳/女性/経理職)
笑顔で周りの人も明るくしてくれる
「職場に笑い上戸な女性がいます。ちょっとした話にも笑ってくれるのが嬉しくて、男性社員はみんな話す機会を狙ってますよ。でも女性社員にも好かれているから、職場のマスコット的存在。笑顔でみんなを明るくしてくれてます」(29歳/男性/会社員)
一生を共に暮らしたいと思える
「笑い上戸な人って、けっこうポジティブな考え方の人が多いと思うんです。だから、結婚したら間違いなく明るい家庭を作れそうな気がする。落ち込んだ時も笑顔で励ましてくれるだろうから、一生を共に暮らしたいと思える人ですね」(27歳/男性/商社勤務)
いい事を運んできてくれそう
「『笑う門には福来る』って昔から言うじゃないですか。友人は何かというと笑いこけるんですけど、彼女と一緒にいると、不思議といい事が起こるんです。自分が笑い上戸じゃないから、彼女と一緒にいて、いい事のおすそ分けにあずかりたい。もちろん大好きだから、一緒にいるんですけどね」(20歳/女性/大学生)
笑い上戸な人をどう思う?【嫌い派の意見】

笑い声がうるさいから苦手…
「計算をしないといけない仕事なのですが、職場に笑い上戸な人がいて困っています。何かというと笑うし、その笑い声がまた大きい。うるさくて仕事に集中できないから、笑い上戸な人は苦手」(25歳/女性/証券会社勤務)
ゲラゲラ笑い続ける人は下品な感じがする…
「笑い上戸なのは別にいいと思うんですけど、ゲラゲラ笑い続けているのはちょっとね。何というか下品が感じがして、その人自身も下品に見えて嫌ですね」(29歳/男性/IT関連職)
へらへらしてる感じがして腹が立つ
「職場に笑い上戸な男性がいるんですけど、なんかへらへらしてる感じがして、見ていてすごく腹が立ちます。『仕事中なんだからへらへらしてないでシャキっとしろ!』と言いたい」(26歳/女性/事務職)
嘘くさく感じる…
「サークル仲間に笑い上戸な女の子がいます。確かによく笑うし、ニコニコしているんだけど、どうも嘘くさい感じがして。いわゆるイケメンの友達の話にはよく笑うけど、ブサメンだとトーンダウンしているような気がします。裏の顔がありそうでイヤ」(21歳/男性/大学生)
笑い上戸な人はモテるって本当?その理由は?

異性に「一緒にいて楽しい」と思わせるから
人は、自分が話したことに笑ってくれるとうれしいと感じます。「この話をしたら笑ってくれるだろう」と考えて意気揚々と話したのに、「ふーん」とか「へえ」といったリアクションをされたら、ガッカリしますよね。
笑い上戸な人がモテると言われる理由は、おもしろい話をしたときだけでなく、「それほどおもしろくないと思うけど…」というような話をしても笑ってくれること。何を話しても笑ってくれるとなれば、一緒にいて楽しくなるのも当然です。
明るい性格というイメージで親しみやすいから
笑い上戸な人は、たいてい明るくてポジティブな性格の持ち主。人は辛い時にはなかなか笑えないものですから、ネガティブな性格の人は笑顔も少なめですよね。
笑顔の人とそうでない人、どちらが親しみやすいかの答えは、明らかでしょう。笑い上戸な人はいつも笑ってニコニコしているため、親しみやすさを感じさせます。
さらに、「笑い上戸=明るい性格」というイメージが浸透していますので、「この人となら楽しく話せそう」と感じさせることも、モテる理由です。
異性に「笑顔が素敵」と感じさせるから
異性の笑顔が素敵と感じる要因に、笑っていない時と笑った時のギャップがあります。このギャップが大きいほど、その笑顔に一瞬でハートを射抜かれてしまうかも?
ただ、笑い上戸な人はいつもニコニコしていることが多いため、ギャップ萌えの要素は少なめです。けれど、いつものニコニコが弾けるような大きな笑顔になったら、大いに萌えるでしょう。
「その素敵な笑顔をずっと見ていたい」と異性に感じさせるのが、モテる理由なのは明らかですね。
相手もポジティブな気分にさせるから
いくら笑い上戸だといっても、その笑い声を聞くには楽しい話をしなければなりません。そのために、自然と楽しい話、おもしろい話はないかと考えるようになります。
その結果、笑い上戸な人自身が自分でも気づかないままに、相手の思考回路をポジティブなものにしてしまうのが特徴。笑い上戸な人と話したあとに楽しい気分になるのは、思考そのものがポジティブになったからでしょう。
意識して相手をポジティブ思考にさせるのではなく、自然とそうさせてしまうのが笑い上戸の人が持つ大きな魅力。まさに、笑いが持つ力を実証していると言えます。
笑い上戸な人が注意すべきこととは?

笑う時の声のトーンを抑える
人の脳は高音よりも低音を好ましいと感じることが、脳科学の研究で分かっているのだとか。その理由は、お母さんのおなかの中にいる時に聞こえている音が、低音だからだと言われています。
確かに、歯医者で歯を削るときのキーンという音や、金属でひっかいたような音を嫌う人は多く、好きという人はほとんど見かけませんよね。笑い声も同じで、高音でキャーキャー笑うと、周囲に不愉快な印象を与えるのは必至です。
笑い上戸なのは仕方ないとしても、笑う時の声のトーンはできるだけ低く抑えるように注意しないといけません。
下品な笑い方にならないよう気を付ける
喉の奥まで見えそうなくらい大口を開けて笑ったり、手や周囲の物を叩いて笑うといった笑い方は、下品な印象を与えます。男性ならまだしも、女性が大口を開けて笑い、口の中が丸見えというのは、どう見ても上品とは程遠いですよね。
笑い声を言葉で表現するのはむずかしいですが、「ゲラゲラ」や「ギャハハ」などの擬音がしっくりくるような笑い方も、注意が必要。女性は下品に見られ、男性は軽薄な印象を与えやすくなります。
下品な笑い方は男女共にマイナスに受け止められる可能性が高いため、笑い方にも気を付けないといけないのは間違いありません。
何でも笑いでごまかさない
笑い上戸な人が注意すべきなのが、笑うことが当たり前になっているために、ついつい笑いでごまかしがちなところです。特に、周囲の人たちが笑い上戸な自分に好意を持ってくれている場合は、仕事の失敗や遅刻をしたときなども、笑ってごまかそうとします。
職場が明るくなるからと笑い上戸を歓迎してくれているとしても、謝らなくてはならないところを笑いでごまかすのはよくありません。謝るべきところはしっかり謝らないと、いつか「笑ってごまかす気か!」と雷が落ちるかも。
笑い上戸にかこつけて何でも笑いでごまかしてきたとしたら、すぐにやめましょう。好かれていたはずが、いつの間にか嫌われてしまう可能性があります。
時には笑いを我慢する必要もある
どんなに笑い上戸でも、時には絶対に笑ってはいけないシチュエーションがあります。葬儀の場を筆頭に、会社の創業記念日などの大事な場では空気を読むことが不可欠です。
学生でも、式典行事などには真剣に取り組む必要があります。社会人ほどではないにしても、場の空気が読めないと恥をかくのは自分。また、周囲の人たちに不快な思いをさせることで嫌われたら、結局は自分自身にマイナスとなって跳ね返ってきます。
笑い上戸だという自覚がある人は、普段からどうしたら笑いを我慢できるかを考えておくことが大事です。
TPOをわきまえた笑い上戸になるのがコツ!

さらに、笑い方に嫌悪感を覚える人もいます。しょっちゅう下品な笑い方をされれば、誰だってイライラしますよね。ついつい笑ってしまうという人は、注意が必要です。
注意すべき点は多いものの、好感を持ってくれる人も多い笑い上戸。TPOをわきまえ、愛される笑い上戸になることが大事です。よく笑う自覚がある人は自分自身を見つめ直し、愛される笑い上戸になってくださいね。
関連する投稿
ブサカワは実はモテる?ブサカワ男女の特徴ともっと魅力的になる方法
「ブサカワ」という言葉を聞いたことはありますか?人から言われると微妙な気持ちになるかもしれませんが、実はブサカワ系の男女はモテると言われています。この記事では、ブサカワ男女の特徴や魅力についてご紹介しています。気になったらぜひチェックしてみてくださいね!
面白い彼女の性格・特徴を徹底解説!モテる理由と笑えるエピソード集
「面白い彼女って、男性からの評判はどうなんだろう?」と気になる女性もいるのではないでしょうか。この記事では、面白い彼女の特徴や、男性の意見をご紹介します。どうやら面白い彼女の魅力は、お笑い芸人のようなユーモラスな面白さだけではないようです。男性から「面白い女性だなー」と思われ、なおかつモテたい女性は必見です!
人たらしの意味と特徴|周りに好かれる人たらしになる方法とは?
「人たらし」という言葉をご存じですか?老若男女を問わず、誰からも好かれる人のことを言います。そんなふうになれたら素敵ですよね。人たらしになるためにはどうしたらいいのでしょうか?この記事では、人たらしになるための方法や、人たらしな人の特徴などを紹介しています。人たらしになりたい人は、読んでみてくださいね。
愛嬌のある女性はモテる?特徴や理由・愛嬌がない人との違いを解説
あなたの身近に、愛嬌があって男性からも人気な女性はいませんか?「ああいう性格だったらモテるんだろうな…」と思ったことがある人も多いはず。しかし、そもそも「愛嬌がある」ってどういうことなのでしょうか?そこでこの記事では、愛嬌がある人の特徴や愛嬌を身につける方法をご紹介します!
B専な人の特徴と心理|意外なメリットやB専診断チェックも紹介!
周りのカップルを見て、「あの人ってもしかしてB専?」と思ってしまうことがよくありますよね。他人事とはいえ、とても気になってしまいます。そのカップルは、なぜ釣り合いの取れる相手とお付き合いしないのでしょうか。今回の記事では、その謎に迫ってみました。
最新の投稿
生成AIエロ画像・エロ動画作成ツール10選|初心者向けの無料ツールも
X(Twitter)やPixivで目にする魅力的なAI生成エロ画像・エロ動画。「自分も作ってみたい」と思っても、どのツールを使えばいいのか、違法性はないのか、不安に感じていませんか? この記事では、生成AIでエロ画像やエロ動画を作成できる厳選ツール10選と、実際の作成手順を初心者向けに徹底解説します。無料で始められるツールから、高品質な画像を生成できる有料ツールまで、それぞれの特徴や使い方を詳しく紹介します。 法的な注意点も含めて、安全に画像生成を楽しむための完全ガイドです。
正常位でうまく挿入できない原因は体位・緊張・体質などさまざま。 本記事では主な理由と、痛みを減らしスムーズに行えるための対策をわかりやすく解説します。
フリスクフェラ完全ガイド|ミンティアフェラや氷フェラとの違いも
フリスクフェラのやり方や魅力を徹底解説します。ミンティアフェラや氷フェラとの違い、刺激の特徴、注意点までわかりやすくまとめた完全ガイドです。初心者でも安心して試せるコツも紹介するのでぜひ参考にして下さい。











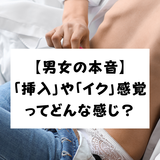



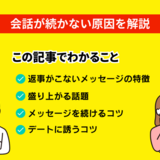
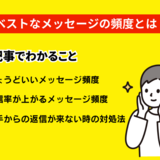

スゴレンは、「男女の恋愛の本音」を集めた恋愛アンケートに基づいて作成した女性向け恋愛コラムを提供しております。さまざまな恋愛シーンで活用できるコンテンツを配信中!